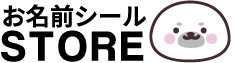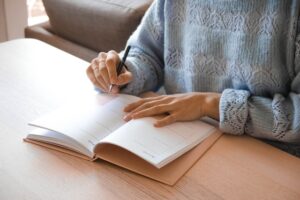赤ちゃんが生まれて幸せな毎日が始まった一方で、多くの親が直面するのが「夜泣き」です。昼間はご機嫌に過ごしていたのに、夜になると突然泣き出し、なかなか泣き止まない…。そんな経験をした方も多いのではないでしょうか。
「この夜泣きはいつまで続くの?」「放置して大丈夫?」「何が原因で泣いているの?」と不安や疑問を抱くのは当然のことです。この記事では、夜泣きの始まる時期や終わる時期、考えられる原因、放置の可否、そして対策方法までを詳しくご紹介します。
目次
夜泣きとは?
夜泣きとは、赤ちゃんが夜中に突然泣き出し、授乳やおむつ替えをしても泣き止まない状態を指します。昼間は元気で病気の症状もないのに、夜になると泣くというのが特徴です。医学的に明確な定義はなく、赤ちゃんの成長の一過程とされています。すべての赤ちゃんに起こるわけではありませんが、多くの家庭で経験する自然な現象です。
夜泣きはいつから始まり、いつまで続く?

一般的に夜泣きが始まるのは 生後6か月頃から1歳半頃 といわれています。早い子では生後3か月頃から夜泣きの兆候が見られることもあり、逆に全く夜泣きをしないまま成長する子もいます。
最も多いのは 1歳前後から1歳半 にかけての時期で、この頃に夜泣きのピークを迎えることがよくあります。そして2歳頃には落ち着いていくケースが多いですが、なかには3歳前後まで夜泣きが続く子もいます。
つまり、「夜泣きはいつまで?」という問いに対する答えは「個人差が大きいものの、ほとんどの子は2歳前後までには落ち着く」というのが現実的な目安です。
夜泣きの原因とは?
夜泣きにはさまざまな要因が絡んでいます。ひとつの原因だけでなく、複数の要素が重なっていることが多いのです。
生理的な要因
睡眠サイクルの未熟さ:赤ちゃんは大人に比べて眠りが浅く、夜中に目を覚ましやすいです。
歯の生え始め:歯茎のむずがゆさや痛みが不快感を引き起こします。
空腹や喉の渇き:夜間の授乳リズムが安定していないと泣くことがあります。
心理的・発達的な要因
日中の刺激:外出や遊びの体験が夢に反映され、夜中に目覚めやすくなることがあります。
分離不安:親と離れることへの不安が夜に強く出る時期があります。
脳の発達:言葉や運動機能が急速に発達する時期は脳が活発になり、眠りが不安定になります。
環境的要因
室温や湿度が合わない
部屋が明るすぎる、物音がする
パジャマや寝具が不快
夜泣きは「赤ちゃんに問題があるから」ではなく、「成長の過程で自然に起こること」と理解しておくと、少し気持ちが楽になるでしょう。
夜泣きを放置しても大丈夫?
「泣かせておけばそのうち寝るのでは?」と思う方もいるかもしれません。確かに、赤ちゃんによってはしばらく泣いたあと自分で寝直すケースもあります。そのため、短時間であれば様子を見る=いわゆる「放置」も悪いとは一概には言えません。
ただし、完全に無視をすると赤ちゃんが不安を感じたり、泣き続けて体力を消耗したりする可能性もあります。特に月齢の低いうちは「泣いたら親が応えてくれる」という安心感が大切です。
結論としては、
新生児〜1歳前後:できるだけ安心させる対応をする
1歳半以降:状況によっては少し様子を見るのも選択肢のひとつ
というバランスを意識すると良いでしょう。
夜泣き対策の工夫
夜泣きを完全になくすことは難しいですが、少しでも和らげる工夫はできます。
基本の対応
抱っこして安心させる
授乳やおむつ替えで不快を取り除く
トントンや子守唄でリズムをつける
環境を整える
部屋を暗く静かにする
エアコンや加湿器で快適な室温・湿度を保つ
同じ布団やお気に入りのタオルなどで安心感を持たせる
生活リズムを整える
日中にしっかり体を動かす
就寝前はテレビやスマホを控え、静かに過ごす
寝る時間をできるだけ一定にする
親の工夫
パートナーや家族と交代で対応し、親自身の睡眠を確保する
抱っこひもやバウンサーを利用して負担を軽減する
「今日は泣いても仕方ない」と割り切る気持ちを持つ
親のメンタルケアも大切
夜泣きで睡眠不足が続くと、親の心身に大きな負担がかかります。「泣き止まないのは自分のせい」と責めてしまう方もいますが、それは間違いです。夜泣きは多くの赤ちゃんにある自然な現象であり、親の努力不足ではありません。
無理をせず、家族や地域のサポートを活用しましょう。ファミリーサポートや一時預かり、家事代行を利用することも立派な育児の選択肢です。同じように夜泣きに悩んだ親の体験談を読むことも、安心につながります。
まとめ
夜泣きは赤ちゃんの成長過程で多くの家庭が経験するものです。始まる時期は生後6か月頃が多く、1歳半〜2歳で落ち着く子が多いですが、個人差があります。原因は睡眠サイクルの未熟さや心理的な不安、環境の影響などさまざまで、必ずしも一つには絞れません。
放置については、月齢や状況に応じて判断することが大切。夜泣き対策としては、安心できる環境を整え、生活リズムを意識しつつ、親自身の心身のケアも忘れないことが重要です。
「夜泣きは必ず終わるもの」ということを心に留めながら、無理をせず、子どもと一緒に少しずつ乗り越えていきましょう。