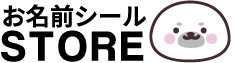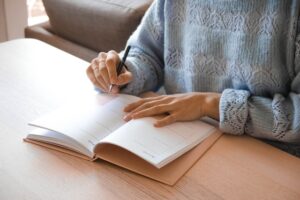小学校に入学すると、子どもの生活リズムは大きく変化します。幼稚園や保育園とは違い、決められた時間に授業を受け、決まった教科の勉強をこなしていく生活が始まります。その中心にあるのが「時間割」。
子どもにとっては新しい学びのスケジュールですが、親にとっても「今日は何の授業?」「体操服はいつ必要?」「給食があるのは?」など、気になることが多くなります。
このコラムでは、小学校の時間割の基本的な仕組みから、学年による違い、持ち物準備のコツや親のサポート方法まで、分かりやすく解説していきます。
目次
小学校の時間割の基本構造
小学校では、時間割に沿って1日を過ごします。1コマあたりの授業時間は、低学年で45分、高学年で50分が一般的。午前中に4時間、午後に1~2時間の授業があるスタイルが多いです。
通常、1校時は8時半~9時15分ごろに始まり、昼休みや給食を挟んで、6校時まで授業がある日もあります。
時間割の中には、主要教科(国語・算数・理科・社会)のほかに、音楽・図工・体育・生活・道徳などもバランスよく組み込まれています。学校によっては、週に1回「総合的な学習の時間」や「クラブ活動」「外国語活動」などが入ることも。
また、曜日によっては朝の集会や掃除の時間などもあり、子どもにとってはかなり盛りだくさんの一日です。
学年ごとに違う時間割
時間割は、学年によって授業時間数や内容が異なります。以下は一般的な傾向です。
【1・2年生】
・基本は午前中中心。週に2〜3日は4時間授業
・体力や集中力に配慮して、午後の授業は少なめ
・「生活」や「音楽」「図工」など、五感を使う授業が多い
【3・4年生】
・5時間授業が日常に
・理科・社会が加わり、教科学習の比重が増える
・専門教員による授業(音楽・体育など)が増える学校も
【5・6年生】
・6時間授業がほぼ毎日
・委員会活動やクラブ活動、卒業行事などが加わる
・英語(外国語)が教科として本格導入される
高学年になるほど授業数が増え、内容も発展的になるため、体力面・学習面でのサポートが重要になります。
地域や学校による違い

時間割には、地域や学校ごとの特色が出ることもあります。
たとえば、土曜日授業を月1回実施している学校がある一方で、完全週休2日の学校も。モジュール授業といって、通常より短い単位(例えば15分×3)で1時間の授業を分割し、集中力を維持させる工夫をしている学校もあります。
また、自治体によっては「朝の読書タイム」や「朝学習」が導入されていたり、ICT教育としてタブレットを活用した授業が時間割に組み込まれている場合も。
保護者としては、子どもの学校の特徴を把握しておくことが大切です。入学時や学期ごとに配られる「時間割表」や「年間計画」をよく確認しましょう。
時間割に合わせた持ち物の準備
時間割を把握することで、忘れ物を防いだり、家庭でのサポートがしやすくなります。たとえば、
図工 → 絵の具セットや粘土
体育 → 体操服・上履き・水筒
音楽 → リコーダー・鍵盤ハーモニカ
理科 → 実験で使うプリントや教材
など、科目ごとに必要な準備が変わってきます。
子ども任せにせず、特に低学年のうちは「前日の夜に一緒に時間割を確認する」ことを習慣化すると安心です。リビングなど目につくところに時間割表を貼り、親子でチェックできる仕組みにしておくと、自然と準備がスムーズになります。
忙しい家庭でもできる!親のサポート術
「毎日時間割を見るのが大変…」「朝はバタバタで確認する暇がない」
そんな家庭でもできる工夫をご紹介します。
前夜にランドセルの中身をチェック(親が一言声をかけるだけでも◎)
「持ち物リスト」を定位置に貼っておく
準備が終わったらチェックマークをつける習慣をつける
お手伝い感覚で兄弟姉妹と確認し合うのも◎
「忘れ物=怒る」ではなく、「どうしたら忘れずにできるか?」という視点で、親が一緒に仕組みを考えていくことで、子どもの自立も育まれます。
よくある疑問Q&A
Q. 時間割は毎週同じ?
A. 基本は曜日ごとに固定されていて、毎週同じ内容。ただし、学期ごとに変更されることがあります。
Q. 急な変更はある?
A. あります。先生の出張や学校行事などで入れ替えが起こる場合も。連絡帳や学校からのお知らせをこまめに確認しましょう。
Q. 家庭で予習・復習は必要?
A. 低学年では基本的に復習中心でOK。時間割に合わせた軽い予習・復習を習慣化しておくと、授業理解度が高まります。
おわりに:時間割は「自立」への第一歩
小学校の時間割は、子どもが「自分で準備をして、計画的に行動する」第一歩でもあります。最初のうちは親のサポートが欠かせませんが、徐々に子ども自身が「明日は何の授業かな?」「準備はこれで合ってるかな?」と考えるようになります。
それは、単なる学校生活のルールを超えて、将来につながる“時間管理能力”や“自己管理能力”の育成につながる大切なステップ。
忙しい毎日の中でも、子どもの時間割に少し目を向けてみると、新たな成長のサインに気づけるかもしれません。