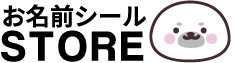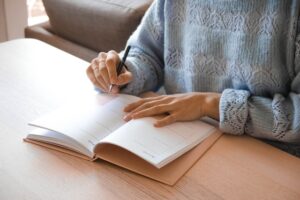「幼稚園は何歳から入園できるの?」
「入園時期、いつにしようかな……」
このようなお悩みはありませんか?
幼稚園は満3歳から入園できますが、最適な時期は子どもによって異なります。年齢制度や年数ごとの特徴を理解することで、最適な入園タイミングの選択ができるでしょう。
そこで、この記事では、幼稚園の入園を検討している方へ向けて入園年齢の基準や保育年数の違いについて解説します。
入園準備や幼稚園選びの参考に、ぜひ最後までご覧ください。
目次
幼稚園は何歳から入園できる?

幼稚園は何歳から入園できるかは、多くの保護者が気になるポイントです。幼稚園への入園には明確な年齢基準があります。
基本的な入園年齢は以下のとおりです。
- 満3歳から入園可能
- 年少・年中・年長クラスにはそれぞれ対象年齢がある
- 4年保育を実施している園もある
それぞれの詳細について説明していきます。
満3歳から入園可能
幼稚園には、満3歳の誕生日を迎えた日から入園可能です。
学校教育法により、幼稚園の入園年齢は満3歳以上と定められています。つまり、子どもが3歳の誕生日を迎えれば、その日から幼稚園に通うことが可能になります。
ただし、満3歳になったからといって、すぐに入園できるわけではありません。園によっては年度途中の入園を受け付けていない場合もあります。また、定員の関係で入園できない可能性もあるため、事前に希望する幼稚園に確認する必要があります。
年少・年中・年長の対象年齢
幼稚園の各クラスには、以下のような年齢区分があります。
クラス名 | 対象年齢 | 学年 |
年少 | 満3歳〜4歳 | 3歳児クラス |
年中 | 満4歳〜5歳 | 4歳児クラス |
年長 | 満5歳〜6歳 | 5歳児クラス |
年齢の区切りは4月1日が基準となります。例えば、年少クラスは4月1日時点で満3歳になっている子どもが対象です。
早生まれの子ども(1月〜3月生まれ)は、同じクラスの中で月齢が低くなります。しかし、個人差もあるため、月齢だけで判断せず、子どもの発達状況を見て入園時期を決めることをおすすめします。
4年保育とは
4年保育とは、満3歳から年長まで4年間幼稚園に通う保育制度のことです。
従来の3年保育(年少〜年長)に加えて、満3歳児クラスを設けている幼稚園が増えています。満3歳児クラスは「プレ年少」や「つぼみ組」などと呼ばれることもあります。
4年保育の大きな特徴は、満3歳の誕生日を迎えたタイミングで入園できるため、翌年4月を待たずに通園を始められることです。例えば、8月生まれの子どもであれば、8月の誕生日以降に入園できます。
幼稚園入園年齢の早見表

何歳から幼稚園に入園できるかを具体的に知りたい方のために、生年月日別の早見表をご紹介します。入園可能な年齢は、子どもの生年月日によって決まります。
幼稚園の年度は4月1日から翌年3月31日までです。4月1日時点での年齢により、入園できるクラスが決定されます。
以下の早見表で、お子さんの生年月日から入園可能な時期を確認できます。
生年月日 | 満3歳入園 (4年保育) | 年少入園 (3年保育) | 年中入園 (2年保育) | 年長入園 |
令和3年4月2日〜令和4年4月1日 | 令和6年誕生日以降 | 令和7年4月 | 令和8年4月 | 令和9年4月 |
令和4年4月2日〜令和5年4月1日 | 令和7年誕生日以降 | 令和8年4月 | 令和9年4月 | 令和10年4月 |
令和5年4月2日〜令和6年4月1日 | 令和8年誕生日以降 | 令和9年4月 | 令和10年4月 | 令和11年4月 |
令和6年4月2日〜令和7年4月1日 | 令和9年誕生日以降 | 令和10年4月 | 令和11年4月 | 令和12年4月 |
例えば、令和5年8月生まれのお子さんの場合、令和8年8月以降に満3歳児として入園でき、令和9年4月から年少クラスに入園可能です。
この早見表を参考に、お子さんに最適な入園時期を検討してください。
※本記事は【2025年時点】の制度に基づいて執筆しています。最新情報は自治体・園にご確認ください。
幼稚園の保育年数の違い

幼稚園は何歳から通わせるかを決める際、保育年数の選択肢について理解することが重要です。幼稚園の保育年数には大きく分けて3つのパターンがあります。
主な保育年数の種類は以下のとおりです。
- 2年保育(年中・年長の2年間)
- 3年保育(年少・年中・年長の3年間)
- 4年保育(満3歳・年少・年中・年長の4年間)
それぞれの仕組みや特徴について詳しく説明していきます。
各保育年数の仕組み(2年・3年・4年)
幼稚園の保育年数は、入園する年齢によって決まります。
保育年数 | 入園年齢 | 通園期間 | 対象クラス |
2年保育 | 満4歳(年中から) | 2年間 | 年中・年長 |
3年保育 | 満3歳(年少から) | 3年間 | 年少・年中・年長 |
4年保育 | 満3歳(誕生日以降) | 4年間 | 満3歳児・年少・年中・年長 |
2年保育は年中クラスから入園するため、4歳になってから幼稚園生活をスタートします。3年保育は最も一般的で、年少クラスの4月から入園します。
4年保育は満3歳の誕生日を迎えた時点で入園できるため、年度途中からの入園も可能です。ただし、4年保育を実施している幼稚園は限られています。
年数ごとの特徴とメリット・デメリット
各保育年数にはそれぞれ異なる特徴があります。
2年保育の特徴
メリットは家庭での時間を長く確保でき、親子の絆を深められることです。また、入園費用を抑えることができます。
デメリットは集団生活の経験が短くなり、小学校入学時の適応に時間がかかる場合があることです。
3年保育の特徴
メリットは適度な集団生活の経験を積め、小学校への準備期間として最適なことです。また、多くの幼稚園で実施されているため選択肢が豊富です。
デメリットは2年保育と比べて費用がかかることです。
4年保育の特徴
メリットは早期から社会性を身につけられ、働く保護者の支援になることです。
デメリットは長期間の費用負担と、実施している園が少ないことです。
子どもの発達に合わせた判断
幼稚園は何歳から通わせるかは、子どもの個性や発達状況を見て決めることが大切です。
判断する際のポイントは、子どもの社会性の発達段階です。他の子どもと遊べるか、基本的な生活習慣が身についているかなどを観察しましょう。
また、言葉の発達も重要な要素です。自分の気持ちを言葉で表現できるようになってから入園すれば園生活により適応しやすくなります。
家庭の状況も考慮要素のひとつです。専業主婦の家庭では2年保育を選択する場合もありますし、共働き家庭では早めの入園も少なくありません。
最終的には、子どもの性格や発達に合わせて、無理のない保育年数を選択することをおすすめします。
幼稚園の入園準備スケジュール

幼稚園は何歳から入園できるかを知った後は、具体的な入園準備のスケジュールを把握することが重要です。幼稚園の入園手続きには決まった流れがあります。
入園準備は入園希望年度の1年以上前から始めることをおすすめします。特に人気の高い幼稚園では、早めの情報収集と準備が必要になります。
下記のスケジュールを参考に、余裕をもって準備を進めましょう。
時期 | 準備内容 | 詳細 |
1年〜1年半前 | 情報収集開始 | 地域の幼稚園リサーチ、口コミ確認 |
5月〜8月 | 幼稚園見学 | 複数園の見学、説明会参加 |
9月〜10月 | 願書提出 | 願書配布・記入・提出 |
11月 | 面接・選考 | 親子面接、入園選考 |
12月〜2月 | 入園決定通知 | 合格発表、入園手続き |
2月〜3月 | 入園準備 | 制服採寸、用品購入、健康診断 |
4月 | 入園 | 入園式、慣らし保育開始 |
満3歳児入園を希望する場合は、誕生日の数ヶ月前から準備を始める必要があります。年度途中の入園は定員に空きがある場合のみ可能なため、早めに希望する園に相談することが大切です。
幼稚園にかかる費用は?

幼稚園は何歳から入園させるかを検討する際、費用面も重要な判断材料になります。幼稚園にかかる費用は、公立と私立で大きく異なります。
幼稚園の主な費用項目は下記のとおりです。
- 入園料(入園時のみ)
- 保育料(毎月)
- 教材費・行事費(随時)
- 制服代・用品代(入園時)
2019年10月から幼児教育・保育の無償化が始まり、多くの家庭で費用負担が軽減されています。ただし、すべての費用が無料になるわけではないため、事前に詳細を確認することが大切です。
費用は保育年数によっても変わるため、2年保育・3年保育・4年保育のどれを選ぶかでも総額が異なります。
※本記事は【2025年時点】の制度に基づいて執筆しています。最新情報は自治体・園にご確認ください。
入園料や保育料の目安
幼稚園の入園料と保育料は、園の種類によって大きく異なります。
費用項目 | 公立幼稚園 | 私立幼稚園 |
入園料 | 5,000円〜20,000円 | 50,000円〜150,000円 |
保育料(月額) | 8,000円〜15,000円 | 25,000円〜40,000円 |
制服・用品代 | 20,000円〜40,000円 | 50,000円〜100,000円 |
私立幼稚園では、上記以外に施設費や冷暖房費などが別途かかる場合があります。また、給食費は無償化の対象外のため、月額3,000円〜6,000円程度が必要です。
バス通園を利用する場合は、月額3,000円〜5,000円のバス代もかかります。習い事や延長保育を利用すると、さらに費用が加算されます。
入園前には各園の費用を詳しく確認し、年間でどの程度の支出になるかを計算しておきましょう。
無償化の対象と条件
幼児教育・保育の無償化により、多くの家庭で幼稚園の費用負担が軽減されています。
無償化の対象となるのは、満3歳から5歳までの全ての子どもです。公立幼稚園では保育料が全額無料になり、私立幼稚園では月額上限25,700円まで支援されます。
ただし、無償化の対象外となる費用もあります。給食費(副食費)、通園送迎費、行事費、教材費などは引き続き保護者負担となります。
預かり保育を利用する場合は、一定の条件を満たせば月額上限11,300円まで無償化の対象になります。条件は両親の就労や介護、求職活動などで「保育の必要性」が認定されることです。
満3歳児の場合は、住民税非課税世帯のみが無償化の対象となるため注意が必要です。
幼稚園選びのポイント

幼稚園は何歳から入園させるかを決めた後は、どの幼稚園を選ぶかが重要になります。幼稚園選びは子どもの成長に大きく影響するため、慎重に検討する必要があります。
重視すべきポイントは下記のとおりです。
- 教育方針と園の雰囲気が家庭の考えと合うか
- 通いやすさと立地条件
- 実際に見学して感じた印象
これらを総合的に判断して、子どもにとって最適な環境を選びましょう。
教育方針と園の雰囲気
幼稚園の教育方針は、子どもの成長に大きな影響を与える重要な要素です。
のびのび系の園では自由な遊びを重視し、お勉強系の園では文字や数字の学習に力を入れています。どちらが家庭の考えと合うかを検討しましょう。
宗教系の幼稚園では、仏教系、キリスト教系、神道系など特定の宗教に基づいた教育が行われます。事前に教育内容を確認することが大切です。
園の雰囲気も重要な判断材料です。先生と子どもたちの関わり方、園内の清潔さ、子どもたちの表情などを観察してください。また、保護者会や行事の頻度が負担にならないかも確認しましょう。
通いやすさと立地
幼稚園の立地と通いやすさは、毎日の生活に直結する重要な要素です。
自宅からの距離と交通手段を具体的に確認しましょう。徒歩、自転車、車、園バスなど、利用可能な交通手段によって負担が大きく変わります。
通園路の安全性も重要です。危険な場所がないか、交通量が多すぎないかを実際に歩いて確認することをおすすめします。
小学校との位置関係も考慮しましょう。同じ小学校に進学する友達が多い幼稚園を選ぶと、子どもにとって安心感があります。雨天時の通園方法についても事前の検討が大切です。
見学で見るべきポイント
幼稚園見学では、パンフレットだけではわからない園の実情を確認できます。
子どもたちの様子では、楽しそうに過ごしているか、先生との関係が良好かを観察してください。施設面では安全性と清潔さが最重要です。遊具の状態、トイレの清潔さ、園庭の広さなどを確認しましょう。
先生の子どもへの接し方や保護者への対応の丁寧さも見てください。給食やお弁当の対応、延長保育の内容、病気時の対応なども具体的に聞いておきましょう。
複数の幼稚園を見学して比較検討することで、子どもに最適な園を選択できます。見学後は家族で話し合い、総合的に判断して決定しましょう。
まとめ:幼稚園入園年齢の判断ポイント
幼稚園は満3歳から入園可能です。年少クラス(3歳)、年中クラス(4歳)、年長クラス(5歳)があり、4年保育では満3歳の誕生日から入園できます。
入園時期は子どもの発達状況と家庭の状況で判断しましょう。早生まれの場合は月齢差を考慮することが重要です。
無償化により費用負担は軽減されていますが、公立と私立で差があります。教育方針、立地、園の雰囲気も選択基準になります。
入園準備は1年前から始め、複数園を見学して比較検討してください。子どもに最適な環境を選び、安心して幼稚園生活をスタートさせましょう。