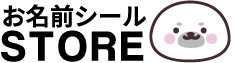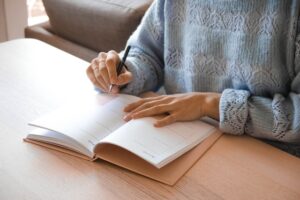赤ちゃんが生まれて半年ほどたつと、今まで穏やかに過ごしていたのに、ある日突然「ママがいなくなると泣き出す」「姿が見えないと大声で呼ぶ」「トイレに行くのも一苦労」といった場面が増えることがあります。これは多くの親が経験する「後追い」と呼ばれる行動です。
初めての子育ての場合、「どうして急に泣くようになったの?」「私がいないとダメなの?」と不安になることもあるでしょう。ですが、後追いは赤ちゃんの心と脳が発達している証拠であり、健やかに育っているサインでもあります。今回は、後追いが始まる時期や理由、いつまで続くのか、そして親がどのように対応していけばよいのかを詳しく見ていきましょう。
目次
後追いとは?
「後追い」とは、赤ちゃんが親や身近な養育者の姿が見えなくなると、不安になって泣いたり、はいはいで追いかけたりする行動のことを指します。心理学的には「分離不安(separation anxiety)」と呼ばれ、愛着形成の一環として自然に現れるものです。
赤ちゃんは生まれたばかりの頃は、自分と周囲の人や物の境界をはっきり認識できていません。しかし月齢が進むにつれて、「この人は自分にとって安心できる存在」という認識が芽生えます。特にママやパパなど、日常的に世話をしてくれる人の存在は特別で、赤ちゃんにとって“安全基地”になります。その安全基地が突然視界からいなくなると、強い不安を感じて泣いてしまうのです。
後追いはいつから始まる?

多くの赤ちゃんで後追いが見られるのは 生後6〜9か月ごろ です。ちょうど「人見知り」が始まる時期と重なることも多く、「知らない人には泣くけれど、ママにはしがみつく」といった行動が増えていきます。
この頃、赤ちゃんの脳には「対象の永続性(object permanence)」という認知の発達が起こります。対象の永続性とは、「見えなくても人や物は存在している」と理解できる能力です。それまでは、ママが視界から消えると「存在そのものがなくなった」と感じていたのが、「確かにいるけれど、今は見えない」という認識に変わります。
しかし、理解できるようになったからこそ「いない!」「どうしよう!」という不安が強くなり、泣き声や後追いという形で表れるのです。
後追いはいつまで続く?
後追いがピークを迎えるのは 1歳前後 と言われます。その後は少しずつ落ち着いていき、一般的には 1歳半〜2歳ごろ になると自然に軽くなることが多いです。
ただし、これはあくまでも平均的な目安であり、赤ちゃんの性格や環境によって大きく個人差があります。活発で好奇心旺盛な子は後追いが短期間で終わることもあれば、甘えん坊な子や家庭中心で過ごす子は長く続くことも珍しくありません。
また、成長の節目や生活環境の変化によって、一度落ち着いた後追いが再び強くなるケースもあります。例えば、保育園への入園、引っ越し、親の復職など、大きな変化があると赤ちゃんが不安を感じ、再び後追い行動が見られることがあります。
後追いが起こる理由
後追いには明確な発達的意味があります。
愛着形成の証拠
赤ちゃんが特定の人を「自分にとって安心できる存在」と認識していることの表れです。後追いがあるということは、それだけ親子の絆が強い証拠でもあります。分離不安の自然なプロセス
赤ちゃんは「自分一人では生きていけない」と本能的に感じています。そのため、大切な養育者が離れると本能的に不安を覚えるのです。発達段階で必要な経験
不安を経験しながらも、少しずつ「離れても必ず戻ってくる」ということを学んでいきます。これは将来の自立につながる大切な学びです。
つまり後追いは「困った行動」ではなく、「成長のステップ」だと捉えると気持ちがぐっと楽になります。
親ができる対応方法
後追いに悩まされると、「トイレにも行けない」「家事が進まない」とストレスを感じることも多いでしょう。ここでは具体的な対応方法を紹介します。
1. 声をかけて安心させる
赤ちゃんにとって「突然いなくなること」が一番の不安要因です。離れるときには「ちょっとトイレ行ってくるね」「すぐ戻るよ」と声をかけましょう。戻ったときも「ただいま」と笑顔で声をかけることで、赤ちゃんは「必ず戻ってくるんだ」と学びます。
2. 少しずつ離れる練習をする
最初から長時間離れるのは難しいので、まずは同じ部屋の中で赤ちゃんの視界から外れる程度から始めましょう。30秒、1分、3分…と徐々に時間を延ばすことで、赤ちゃんは少しずつ安心して待てるようになります。
3. 安心できるグッズを用意する
お気に入りのおもちゃやブランケット、ママの匂いがするハンカチなどがあると、不安が和らぎます。いわゆる「安心毛布」の役割を持つアイテムを活用しましょう。
| |
4. 他の大人に慣れさせる
祖父母や保育士など、親以外の大人と少しずつ過ごす経験も有効です。最初はママやパパが一緒にいる状態から始め、徐々に短時間預けるなど、段階を踏んで慣れさせるとよいでしょう。
5. 親が焦らない
「こんなに泣かれては困る」と焦ると、赤ちゃんはその不安を敏感に感じ取ってしまいます。「いつかは必ず落ち着くもの」と理解して、気持ちに余裕を持つことが大切です。
よくある悩みと解決ヒント

「トイレにも行けない!」
→ 短時間の練習を繰り返す。ドア越しに声をかけるだけでも安心感を与えられる。「家事が進まない」
→ 抱っこひもで移動する、キッチンの横にベビーサークルを置くなど、赤ちゃんの視界に入るよう工夫する。「保育園で泣き続けて心配」
→ 多くの子は時間とともに慣れていく。先生に様子を聞きつつ、家庭では安心できる時間をたっぷりとる。「祖父母に預けられない」
→ 最初はママと一緒に祖父母と遊ぶ時間を設け、少しずつ離れる練習を。
まとめ
赤ちゃんの後追いは、親にとっては負担に感じることもありますが、心と脳がしっかり成長している証です。
始まるのは生後6〜9か月ごろ
ピークは1歳前後
多くは1歳半〜2歳ごろには落ち着く
愛着形成や自立に向けた大切なプロセス
対応の基本は「安心させる」「少しずつ慣らす」「親が落ち着く」の3つです。
「今しか見られない姿」と考えると、後追いの大変さも少し違って見えてくるかもしれません。赤ちゃんが親を信頼している証として受け止め、温かく見守っていきましょう。