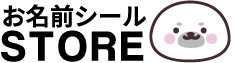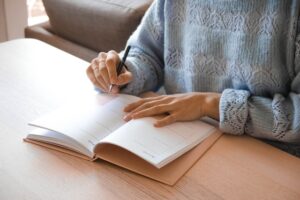赤ちゃんが生まれてから100日ほどが経つと、少しずつ笑顔が増え、家族の暮らしにも新しいリズムが生まれてきます。そんな節目に行う伝統行事が「お食い初め(おくいぞめ)」です。
「一生食べるものに困らないように」という願いを込めて行うお祝いで、赤ちゃんに初めて食事を“食べさせる真似”をします。
しかし実際に迎える時期になると、「お食い初めっていつやるの?」「どんな料理を準備すればいい?」「赤ちゃんの服装は?」と悩む方も多いものです。
この記事では、お食い初めの意味や時期、やり方、服装、記念の残し方まで、わかりやすく解説します。
目次
お食い初めとは?意味と由来
お食い初めは、赤ちゃんが生後100日前後に行う日本の伝統行事で、「百日祝い(ももかいわい)」とも呼ばれます。
「赤ちゃんが一生食べ物に困らないように」という願いを込めて、家族が赤ちゃんの口元に料理を運ぶ儀式です。
この風習の起源は平安時代にまでさかのぼります。当時の貴族たちは、赤ちゃんの成長を祝う行事として「真魚始め(まなはじめ)」と呼ばれる儀式を行っていました。そこから庶民にも広がり、形を変えながら現代まで受け継がれています。
お食い初めの儀式では実際に食べるわけではなく、「食べる真似」をするのが特徴です。まだ歯が生えていない赤ちゃんに、「食べる力」「生きる力」を授ける象徴的な行事といえるでしょう。
お食い初めはいつやる?時期の目安と数え方

お食い初めは、一般的に生後100日目に行います。
ただし、必ずしも100日ぴったりでなくても大丈夫です。赤ちゃんや家族の体調、祖父母の予定などを考慮して、100日を中心に前後1〜2週間程度のタイミングで行う家庭が多いです。
また、地域によっては110日目や120日目に行うこともあります。おじいちゃん・おばあちゃん世代に聞いてみると、昔の風習にまつわる話を教えてもらえるかもしれません。
日取りを決めるときには、「大安」「先勝」などのお日柄を気にする家庭もありますが、最近では週末や家族が集まりやすい日を選ぶ方が主流です。
無理なく、みんなが笑顔でお祝いできる日を選びましょう。
お食い初めのやり方と準備するもの
お食い初めでは、赤ちゃんの前に「祝い膳」を用意し、家族の中で最も年長の人(長寿を象徴する人)が、食べ物を口元に運ぶ真似をします。ここでポイントとなるのが、料理と食器の準備です。
お食い初め膳の基本構成
お食い初めの料理は、一汁三菜が基本。伝統的には以下のような内容です。
赤飯:お祝いごとの定番。小豆の赤色が邪気を払うとされます。
尾頭付きの鯛:縁起の良い「めでたい」にかけて。
煮物:季節の野菜を使った煮物で、根菜には「根を張る」意味も。
香の物(漬物など):口直しの意味を持ちます。
吸い物(はまぐりなど):夫婦円満や健やかな成長を願う象徴。
これらに加えて用意するのが、「歯固めの石」です。
「丈夫な歯が生えますように」という願いを込め、神社の境内などから小さな石を借りて使います(使用後は洗って返却します)。赤ちゃんの口元に軽く当てる真似をして行います。
食器の準備
正式には漆塗りの「お食い初め膳」を使います。
男の子は赤色、女の子は黒色の器を使うのが古くからの習わしですが、最近では木製や陶器のもの、ベビー用の可愛いセットも人気です。通販でも「お食い初めセット」として販売されています。
食べさせ方と順番
食べさせる真似は、「養い親」や「祖父母のうち最も長寿の方」が担当するのが伝統。
順番にも決まりがあり、
「ご飯 → お吸い物 → ご飯 → 魚 → ご飯」
のように3回繰り返すと良いとされています。
ただし現代では、あまり形式にこだわらず、楽しく家族で祝うスタイルが主流です。赤ちゃんが泣いてしまったり、眠ってしまった場合は時間をずらしてOK。
「みんなで赤ちゃんの成長を祝う」という気持ちを大切にしましょう。
お食い初めの服装はどうする?赤ちゃん・家族別に紹介
赤ちゃんの服装
赤ちゃんの服装は、フォーマル感と快適さのバランスが大切です。
男の子:袴風ロンパースや和風カバーオールが人気。
女の子:被布セットやレースのドレス、ワンピースなど華やかな装い。
写真撮影をするなら、着物風デザインやお祝い感のあるカラー(赤・白・金など)を選ぶと映えます。
ただし、ミルクやよだれで汚れることもあるので、着替えを1〜2着用意しておくと安心です。
両親・祖父母の服装
フォーマルすぎる必要はありませんが、「清潔感」と「統一感」を意識すると写真がきれいにまとまります。
母親:ワンピースやブラウスにスカートなど上品なコーデ。
父親:ジャケットスタイルやシャツで清潔感を演出。
祖父母:落ち着いた色合いのセミフォーマルがベター。
自宅で行う場合はカジュアルでも問題ありませんが、家族写真を撮る場合は全員の服装のトーンを合わせると統一感が出ます。
お食い初めはどこでやる?自宅・料亭・写真スタジオの選び方
お食い初めは、主に次の3つのスタイルがあります。
自宅で行う
家族のペースで行えるため、赤ちゃんがリラックスできるのが最大のメリット。料理を手作りしたり、デリバリーを活用したりと自由度も高いです。料亭やホテルで行う
お祝い膳付きのプランが多く、準備の手間が省けます。落ち着いた個室で行えるため、祖父母との食事会にも最適です。写真スタジオで行う
「お食い初め+記念撮影」がセットになったプランも人気。衣装やお膳をすべて用意してもらえるので、手ぶらで特別な記念写真を残せます。
| |
どのスタイルにもメリットがあるので、家族の都合や希望に合わせて選びましょう。
記念の残し方・写真の撮り方アイデア
お食い初めは、赤ちゃんの「初めての節目」を記録に残す絶好のチャンスです。
当日の写真は、次のようなポイントを意識して撮影すると素敵に仕上がります。
赤ちゃんの表情をアップで撮る
お膳や鯛、歯固め石など、料理の全体写真を撮る
家族全員で集合写真を撮る
100日ボードや名前入りスタイを小物として使う
また、手形・足形をとって記念ボードを作るのもおすすめ。
SNSでは「#お食い初めフォト」「#100日記念」などのハッシュタグで投稿する人も多く、成長の節目を共有する文化が広がっています。
まとめ
お食い初めは、赤ちゃんの健やかな成長を願うだけでなく、家族が一堂に会して「生まれてきてくれてありがとう」と気持ちを伝える大切な行事です。
厳密なルールや形式にこだわらず、赤ちゃんや家族のペースで楽しくお祝いするのが一番。
思い出に残る写真を撮ったり、手作りのお膳を囲んだりと、それぞれの家庭らしい形でお祝いしましょう。
一生に一度の「お食い初め」。
赤ちゃんの笑顔とともに、家族の温かい思い出として残る時間になるはずです。