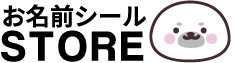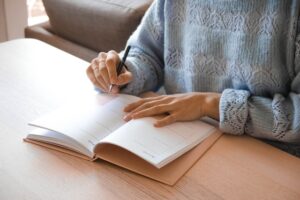「昨日まではニコニコしていたのに、今日は何をしてもイヤ!って泣き叫んでる…」
そんな変化に戸惑った経験はありませんか?
ごはんを出しても「イヤ」、お風呂に誘っても「イヤ」、服を着るのも「イヤ」…。ママやパパにとっては衝撃的なこの“イヤイヤ攻撃”ですが、実はこれは子どもが健やかに育っている証でもあります。
この時期を「イヤイヤ期」または「第一次反抗期」と呼び、多くの親が一度は悩み、そして乗り越えてきた育児の一大イベントなのです。
目次
イヤイヤ期ってなに?その意味と背景
イヤイヤ期とは、子どもの自我が芽生え、自分の意思を持ち始める時期に起こる行動のことです。
まだうまく言葉で気持ちを伝えられない年齢の子どもは、「やりたいけどうまくできない」「思い通りにならない」といった葛藤を、「イヤ!」というシンプルな言葉や泣き叫ぶ行動で表現します。
大人から見ると理不尽に思えることでも、子どもにとっては「自分を主張する大切な手段」。この時期は、心の成長が急速に進んでいる証拠でもあるのです。
イヤイヤ期はいつから始まるの?

一般的に、イヤイヤ期は1歳半〜2歳ごろに始まり、3歳〜4歳頃まで続くと言われています。
早い子では1歳を過ぎたころから「イヤ」が始まり、遅い子では3歳を過ぎてから始まることも。兄弟姉妹でもタイミングが異なることが多いため、「うちの子、早すぎる?」や「まだ始まらないけど大丈夫?」と焦る必要はありません。
個人差が大きい時期なので、目の前の子どもが何を伝えたがっているのか、どんな風に世界を見ているのかを意識して接することが大切です。
どんな行動が「イヤイヤ期」なの?
イヤイヤ期の行動は、まさに「なんでもイヤ!」。日常のあらゆる場面でその姿が見られます。たとえば:
ごはんを用意しても「食べない!」
おむつを替えようとすると「逃げる!」
公園から帰りたくないと大泣き
自分でやりたがるのに、うまくできなくて怒る
とにかく何を聞いても「イヤ」と返ってくる
これらの行動は、子どもが自分の世界を確立しようとしている証拠です。「こうしたい」「これはイヤだ」と感じられるようになったという、心の成長のあらわれです。
イヤイヤ期との向き合い方:親の心構え
イヤイヤ期の子どもに対して、つい「なんでそんなにわがままなの!?」とイライラしてしまうこともあるでしょう。でも、大人の視点で押さえつけてしまうと、子どもはますます反発したり混乱したりしてしまいます。
大切なのは、「気持ちを受け止める姿勢」です。
「〇〇したくないんだね」「今は違う気分なのかな」と、子どもの気持ちに寄り添ってあげることで、本人も安心し、落ち着くことがあります。
また、選択肢を与えるのも有効です。
「今からお風呂に入るよ」ではなく、「パンダさんのタオルとクマさんのタオル、どっち使う?」と聞くと、自分で選べることに満足してスムーズに進むこともあります。
よくある悩みと対処法
親たちからよく聞くのが、「出かけようとしたら着替えを拒否して大泣き」「買い物中に床に寝そべって動かない」「抱っこもイヤ、歩くのもイヤで進まない」といった悩みです。
こんなときは、すぐに言うことを聞かせようとせず、まずは子どもの気持ちを受け止めましょう。「そうだね、まだ帰りたくなかったんだね」と言うだけでも、子どもは気持ちを理解してもらえたと感じて落ち着くことがあります。
そして何より、親自身が疲れていると対応する余裕もなくなってしまいます。
そんなときは、無理に完璧を目指さず、思いきって家事を手抜きしたり、パートナーや家族、保育園などに頼ったりして、自分自身のリフレッシュ時間を作ることも大切です。
イヤイヤ期はいつ終わるの?
永遠に続くように感じるイヤイヤ期ですが、実はほとんどの子が3歳〜4歳ごろには落ち着いてきます。
言葉の発達が進むことで、自分の気持ちをうまく言葉で表現できるようになり、イヤ!と叫ばずに「こうしたい」と伝えられるようになるからです。
また、親子のコミュニケーションの積み重ねによって、信頼関係が築かれ、「イヤイヤしなくても分かってもらえる」と感じられるようになるのです。
おわりに:今だけの「成長の証」を大切に
イヤイヤ期は、子どもの「心の成長」がぎゅっと詰まった貴重な時間。
もちろん、大人にとってはストレスフルで、大変な時期でもあります。でも、この時期を乗り越えることで、子どもは自分らしさを育て、親子の絆も深まっていきます。
「この子なりに頑張ってるんだな」と、少し距離を取って見てみると、心が軽くなることもあるかもしれません。
ひとりで抱え込まず、まわりの助けを借りながら、親子でこの時期を乗り越えていきましょう。
イヤイヤも、やがて思い出に変わる日がきっと来ます。